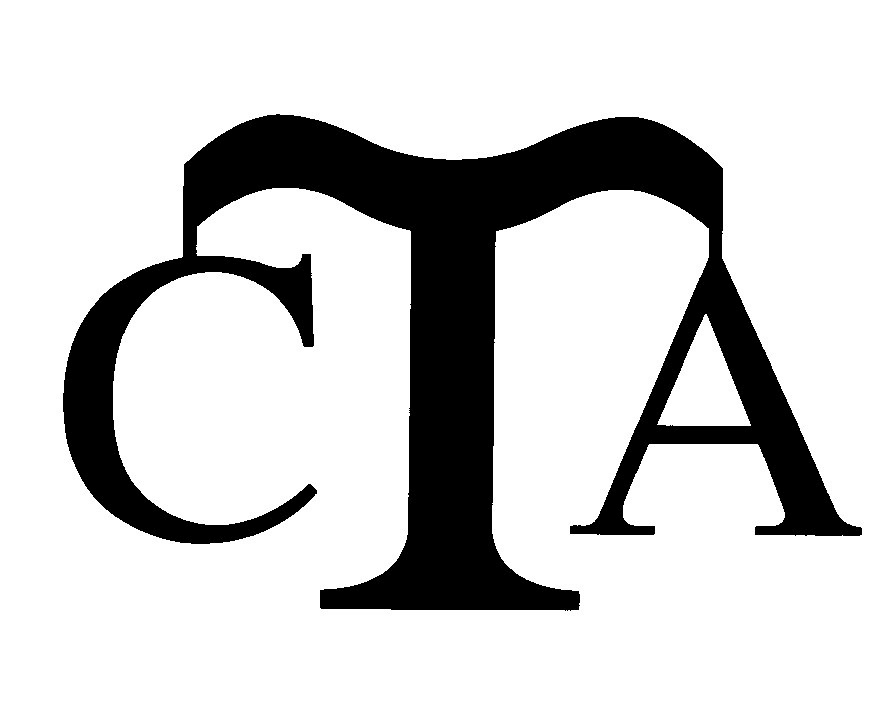未来を拓く熱測定学会の変革
令和8年新春,会員の皆様におかれましては,お健やかに新年をお迎えのことと拝察いたします。本年が皆様にとりまして実り多き年となりますよう,謹んでお祈り申し上げます。
本学会は,熱測定という専門性の高い分野の研究者によって構成されていますが,学会設立から50年以上,さらに討論会の開催から60年以上にわたる,長い歴史と確かな伝統を有する学術団体です。これまで学会を支えてこられた先達の先生方の卓越したご業績にあらためて深い敬意を表するとともに,日頃より多大なご尽力をいただいている会員の皆様に心より感謝申し上げます。今後も新たな時代の要請に応えながら,学会活動をさらに発展させてまいります。
本年度は,本学会が一般社団法人へ移行する過渡期にあたり,移行スケジュールに基づいて法人化への準備を進めていきます。今後,幹事会(法人化準備 WG)や各委員会において,定款(案)や組織図案などについて審議を行い,会員の皆様へ順次ご提示し,本学会の法人化に向けたご意見・ご提案を伺う予定です。法人化は,本学会として大きな体制変革となる重要な転機ではありますが,将来のさらなる発展を見据えた上で欠かすことのできない措置であると考えています。つきましては,会員の皆様のご理解とご支援をいただけますと幸いに存じます。
現在,学会が共通して抱える課題は数多く存在します。そうした主要な課題に対して,本学会としてどのように向き合い,対応していくかが鍵となります。
- 学会を取り巻く研究者人口の変化と会員減少への対応
- 経済情勢の変化による財政面の課題と持続的運営
- 学会活動のDX・オープンサイエンス対応とデジタル資産の活用
(1) 学会を取り巻く研究者人口の変化と会員減少への対応
最初の課題は,会員数の減少と高齢化です。本学会においても,1990年初頭には1,000名に迫る会員数を有していましたが,近年では500名弱と半数ほどにまで減少しています。背景には,熱研究分野全体の研究者人口が伸び悩んでいることに加え,若手研究者の参入が減少しているという構造的な問題があります。このような状況を踏まえると,若手研究者が学会に参画する意義やメリットをより明確に示し,研究活動の魅力を伝える仕組みを整えることが急務となります。例えば,若手向けの企画や支援制度の充実,研究発表機会の拡大など,次世代を育成する観点からの取り組みが今後ますます重要になります。
(2) 経済情勢の変化による財政面の課題と持続的運営
二つ目の課題は,学会運営における財政基盤の確保です。本学会では,これまで会費改定やコロナ禍での経費節減といった努力により,過去の赤字状態を解消することができました。しかし,昨今の物価・人件費の上昇により,討論会の開催費用や学術誌出版に必要なコストが増大しており,収支を健全に維持するための工夫がかつて以上に求められています。今後は,事業の効率化や収益構造の見直しなど,合理化を組み合わせた持続可能な運営体制を検討する必要があります。特に,学術誌の在り方や会務のデジタル化など,経費削減と価値向上を両立する取り組みが重要になると考えます。
(3) 学会活動のDX・オープンサイエンス対応とデジタル資産の活用
三つ目の課題として,学会活動の DX(デジタルトランスフォーメーション)推進が不可欠です。研究成果のオープンアクセス化や研究データ共有を含むオープンサイエンスへの対応は,学術界全体の潮流となりつつあり,本学会においても例外ではありません。編集委員長在任時には,会誌『熱測定』の全巻をJ-STAGEに完全登載し,50年以上にわたる研究成果にすべてDOI(Digital Object Identifier)を付与することが実現しました。これは,本学会が誇るべき重要なデジタル資産であり,現在,幹事会ではこの資産を最大限に活用できるよう学会ホームページの改修が検討されています。さらに,昨年11月には,機械学習やデータ科学を活用した材料探索・特性予測を扱うMI(Materials Informatics)に関する第59回熱測定ワークショップを開催し,ビッグデータの利活用も本格的に始動しています。これらの取り組みは,学会の新たな価値創造につながる重要なステップであり,将来に向けた基盤整備として期待されます。
これらに加えて,国際連携活動の推進,多様性・公平性(DEI)の不足解消,社会との接点強化などに対しても対応を考えていく必要があります。
熱測定研究は,物質の本質へと迫る普遍的学問であると同時に,未来の科学技術を支える知的基盤として,揺るぎない重要性を有しています。本学会においても,熱測定討論会,学会誌『熱測定』,各種グループ活動,ワークショップや講演会など,多彩な学術活動がその基盤を成してきました。今後は,これらの取り組みを一層充実・深化させ,会員の皆様にとってより魅力ある学会へと発展させるべく,鋭意努力してまいる所存です。引き続き,皆様のご支援とご協力を賜りますよう,心よりお願い申し上げます。
日本熱測定学会 会長 松木 均